海外マーベルの有名アメコミ「スパイダーマン」とのコラボ。MTG x スパイダーマンにおけるドラフトの攻略についてです。
2ピックドラフトが本格実装された初のセットなんですが、コスパが良かったので、普段より多めに回してミシック600位くらいまで上げての所感になります。
お互いのレアをぶつけ合う友好2色環境であり、白緑のウェブスリングと蜘蛛が環境を牽引しています。
MTGアリーナでは版権の問題から「領界路の彼方」となっており、イラストと一部のテキストが変更されていますが、本稿では原型である「スパイダーマン」前提になっています。
目次
概要
2ピックのコツ
公式が設計段階で2ピックを意識したセットであると述べており、近年では珍しい友好2色のみを意識したセットになっています。

今回、初めての実装となる2ピックですが、決め打ちドラフトをすると失敗しやすい一方、卓の流れを見てデッキを構築する受けドラフトだと戦績が安定します。
パックの中から2枚ピックなので、上家からの主張が見えやすく、下家の色をコントロールしやすい利点があります。パックの中で取りあえず強いカードを取るのは基本ですが、下家にどの色のカードを流すかを考慮しておくと、プレミアドラフトよりも上手くいきます(あくまで対人ドラフトの話です)。
例えば、初手のパックにプレイアブルな緑のカードが4枚~5枚あった場合、緑および緑友好色のデッキは下家と被るリスクが高まります。プレアイブルなカードが2枚~3枚くらいの色を狙い撃ちし、上からの主張を見つつ、最終的な色を決めると良いです。
なお、スパイダーマン環境は明確な赤一弱の状況なので、下家が赤を握ってくれるのがベストです。自分自身はできるだけ赤に触れないようにしましょう。赤の除去などを流して、下を赤く染めたいです。
友好色レア環境
登場するレアが全体的に強力で、取りあえず場に出れば活躍してくれることが多いです。
最近のセットだと「タルキール龍嵐録」に近いものの、IIHの中央値、偏差共に少しずつ上回るので、それ以上にお互いにレアを出し合って戦う展開になりやすい。
歴代ワーストクラスのパック運ドラフトだった「ファイナルファンタジー」程ではないものの、レア格差の影響はかなり出やすいセットなので、レアを最大限に活用できる形を模索したいです。
友好色についてはマナ基盤も比較的に整えやすいので、強力なカードをタッチしやすく、特に緑軸だと黒ダブルシンボルみたいな無茶なタッチもできます。

そしてレアゲーになりやすい都合上、それを排除できる各種除去の価値も大きいです。除去の枚数さえあればクリーチャーが小粒でも勝てますし、逆に除去が少ないとレア満載でも辛い時が多いです。
強いレアを拾うのを基本としつつも、テンポ負けしない小型クリーチャー、そしてボムに対応できる除去を意識してピックすると良いです。
ウェブスリングとコンバット
ウェブスリングは過去に存在していた忍術にも似たギミックで、タップ状態のクリーチャーを手札に戻すことで、正規より少ないマナコストで唱えられます。

スパイダーマン・インディア
(3)(緑)(白)
伝説のクリーチャー - 蜘蛛(Spider)・人間(Human)・英雄(Hero)
4/4
ウェブスリング(1)(緑)(白)(あなたがコントロールしていてタップ状態であるクリーチャー1体をオーナーの手札に戻すなら、この呪文を(1)(緑)(白)で唱えてもよい。)パヴィトラの奉仕 ― あなたがクリーチャー呪文1つを唱えるたび、あなたがコントロールしているクリーチャー1体を対象とする。それの上に+1/+1カウンター1個を置く。ターン終了時まで、それは飛行を得る。
クリーチャーを手札に戻すのはデメリットではあるものの、出たとき能力を再利用できるので、上手く使えば更なるアドバンテージにも繋がります。
出たときに1ドローや、出たときに+1/+1カウンターをばら撒く、出たときに土地を1枚サーチするなど、長期戦に強くなるアクションなので、狙えるときに狙っておきたいです。
逆を言えば、相手が再利用を狙っている状況ならブロッカーを積極的に立てる必要がありますし、多少不利でもブロックせざるを得ない状況も発生します。
警戒や接死持ちのクリーチャーが意外と役立ったり、計画を狂わせるジャイグロ系のスペルが普段より強かったりする一因になっています。
主だったアーキタイプ
| 中心色 | 評価 | 方向性 |
|---|---|---|
(アゾリウス) | B | 改善を利用したアグロ +1/+1カウンターを重視(参考) |
(オルゾフ) | – | – |
(ボロス) | – | – |
(セレズニア) | A | ウェブスリング特化 マルチアンコが強力で一番人気(参考) |
(ディミーア) | B | 墓地肥やしコントロール 悪人に依存した部族色も強いです(参考) |
(イゼット) | – | – |
(シミック) | – | – |
(ラクドス) | C | 大混乱に特化 かなり不安定でデッキになりにくい |
(ゴルガリ) | – | – |
(グルール) | C | 赤の大混乱が不発になりやすく 除去も白に比べて貧弱 |
緑軸であれば、対抗色でもデッキになることはあるものの、基本的には友好色でデッキを組みたいです。
また赤系が明らかに凹んでいる状態なので、それを避けたアゾリウス、ディミーア、セレズニアを取り合う形になるので、速い段階で色を決めて、下家をコントロールするのが良いでしょう。
各色の状況
白(純粋強) > 緑(レア受け〇) = 黒(除去〇) > 青 >>> 赤(ブッチギリ最弱)
白
優秀な除去を有する色で、白青、白緑と受けが広いのが強みです。


スパイダーUK
(3)(白)
伝説のクリーチャー - 蜘蛛(Spider)・人間(Human)・英雄(Hero)
3/4
ウェブスリング(2)(白)(あなたがコントロールしていてタップ状態であるクリーチャー1体をオーナーの手札に戻すなら、この呪文を(2)(白)で唱えてもよい。)あなたの終了ステップの開始時に、このターンに2体以上のクリーチャーがあなたのコントロール下で戦場に出ていた場合、カード1枚を引き、2点のライフを得る。


ペニーが操縦するSP//dr
(3)(白)(青)
伝説のアーティファクト・クリーチャー - 蜘蛛(Spider)・英雄(Hero)
4/4
警戒ペニーが操縦するSP//drが戦場に出たとき、クリーチャー1体を対象とする。それの上に+1/+1カウンター1個を置く。あなたがコントロールしていて改善されているクリーチャー1体がプレイヤー1人に戦闘ダメージを与えるたび、カード1枚を引く。


ウェブの戦士
(4)(緑/白)
クリーチャー - 蜘蛛(Spider)・英雄(Hero)
4/3
このクリーチャーが戦場に出たとき、あなたがコントロールしていてこれでない各クリーチャーの上にそれぞれ+1/+1カウンター1個を置く。


不意の一撃
(1)(白)
インスタント
攻撃やブロックしているクリーチャー1体を対象とする。それを破壊する。


デイリー・ビューグル社の記者
(3)(白)
クリーチャー - 人間(Human)・市民(Citizen)
2/3
このクリーチャーが戦場に出たとき、以下から1つを選ぶ。・称賛記事 ― クリーチャー最大2体を対象とする。それらの上にそれぞれ+1/+1カウンター1個を置く。


スカイワード・スパイダー
(白/青)(白/青)
クリーチャー - 蜘蛛(Spider)・人間(Human)・英雄(Hero)
2/2
護法(2)(このクリーチャーが対戦相手がコントロールしている呪文や能力の対象になるたび、そのプレイヤーが(2)を支払わないかぎり、その呪文や能力を打ち消す。)このクリーチャーが改善されているかぎり、これは飛行を持つ。(装備品(Equipment)やあなたがコントロールしているオーラ(Aura)がついているかカウンターが置かれているクリーチャーは改善されている。)


壮大な作戦
(1)(白)
インスタント
以下から1つを選ぶ。・あなたがコントロールしているクリーチャー1体を対象とする。それの上に+1/+1カウンター1個を置く。ターン終了時まで、それは呪禁を得る。


糸巻き
(2)(白)
エンチャント
このエンチャントが戦場に出たとき、対戦相手がコントロールしていて土地でないパーマネント1つを対象とする。このエンチャントが戦場を離れるまで、それを追放する。
クリーチャーとしては《スカイワード・スパイダー》と《デイリー・ビューグル社の記者》が強力で、今回の白は+1/+1カウンターを活用した高速アグロを得意とします。
また、コモン呪文の《壮大な作戦》は攻防の要となる1枚です。
大型クリーチャーに対する除去としても優秀なんですが、呪禁で自身のクリーチャーを守れるのも強力です。普段ならアンコモン枠だろうカードなんですが、何故かコモンで収録されているので、白躍進の原動力となっています。
白緑のマルチアンコが強力で、緑のおかげでレアの自由度があるので1番人気です。白緑タッチまで含めると圧倒的な多数派になります。
次点の白青の改善アグロになっても十分に戦えるので、白絡みのレアは取りやすいです。ただし、白青は他の色をタッチしにくこと、飛行アグロの構成になるので、白緑とは組み方が異なります。
緑
マナ基盤の強さがレア環境での助けになってくれる色です。


被害対策の作業員
(3)(緑)
クリーチャー - 人間(Human)・市民(Citizen)
3/3
このクリーチャーが戦場に出たとき、以下から1つを選ぶ。・復旧 ― あなたの墓地にありマナ総量が4以上であるカード1枚を対象とする。それをあなたの手札に戻す。


見事な連携
(3)(緑)
インスタント
あなたがマナ総量が4以上であるパーマネントをコントロールしているなら、この呪文を唱えるためのコストは(2)少なくなる。あなたがコントロールしているクリーチャー1体か2体を対象とし、対戦相手がコントロールしているクリーチャー1体を対象とする。ターン終了時まで、それらの前者はそれぞれ+1/+0の修整を受ける。それらの前者はその後者にそれぞれ、それら自身のパワーに等しい点数のダメージを与える。


壁登り
(3)(緑)
エンチャント
このエンチャントが戦場に出たとき、到達を持つ緑の2/1の蜘蛛(Spider)クリーチャー・トークン1体を生成する。その後、あなたがコントロールしている蜘蛛1体につき1点のライフを得る。あなたがコントロールしているすべての蜘蛛は+1/+1の修整を受け、防衛を持つクリーチャーにはブロックされない。


ライノの猛威
(赤/緑)
ソーサリー
あなたがコントロールしているクリーチャー1体を対象とし、対戦相手がコントロールしているクリーチャー1体を対象とする。ターン終了時まで、その前者は+1/+0の修整を受ける。その前者はその後者と格闘を行う。これにより対戦相手がコントロールしているクリーチャーが余剰のダメージを受けたとき、マナ総量が3以下でありクリーチャーでないアーティファクト最大1つを対象とする。それを破壊する。


プロレスラー
(3)(緑)
クリーチャー - 人間(Human)・戦士(Warrior)・パフォーマー(Performer)
4/4
このクリーチャーが戦場に出たとき、宝物(Treasure)トークン1つを生成する。(それは「(T),このトークンを生け贄に捧げる:好きな色1色のマナ1点を加える。」を持つアーティファクトである。)このクリーチャーは、2体以上のクリーチャーにはブロックされない。


ブルックリンの空想家、スパイダーマン
(4)(緑)
伝説のクリーチャー - 蜘蛛(Spider)・人間(Human)・英雄(Hero)
4/3
ウェブスリング(2)(緑)(あなたがコントロールしていてタップ状態であるクリーチャー1体をオーナーの手札に戻すなら、この呪文を(2)(緑)で唱えてもよい。)これが戦場に出たとき、あなたのライブラリーから基本土地カード1枚を探し、タップ状態で戦場に出す。その後、ライブラリーを切り直す。


果敢な恐竜、スパイダーレックス
(4)(緑)(緑)
伝説のクリーチャー - 蜘蛛(Spider)・恐竜(Dinosaur)・英雄(Hero)
6/6
到達、トランプル護法(2)(このクリーチャーが対戦相手がコントロールしている呪文や能力の対象になるたび、そのプレイヤーが(2)を支払わないかぎり、その呪文や能力を打ち消す。)


蜘蛛の顕現
(1)(赤/緑)
クリーチャー - 蜘蛛(Spider)・アバター(Avatar)
2/2
到達(T):(赤)か(緑)を加える。
《蜘蛛の顕現》は2マナのマナクリーチャーながら、到達持ちで飛行アグロに対しての備えになりますし、4マナ以上でアンタップするので、中盤の展開を見た目以上に助けてくれます。
《プロレスラー》と《ブルックリンの空想家、スパイダーマン》は多色サポートとして優秀で、強力なボムを強引に採用しやすくなります。盤面を支えつつ、後発に繋げる優良コモンです。
除去については頼りないよりの色なんですが、アンコモンの《見事な連携》と《ライノの猛威》があるので、それらは積極的に取っておきたいです。
できるだけ一番人気の白緑にしたいですが、色マナさえあればいろんな形が取れるので、場合によっては対抗色のデッキも考慮したい変幻自在さが魅力だと思います。
黒
リミテッド環境の黒では毎度おなじみのパターンですが、除去の強さが本質の色です。


スパイダーマン・ノワール
(4)(黒)
伝説のクリーチャー - 蜘蛛(Spider)・人間(Human)・英雄(Hero)
4/4
威迫あなたがコントロールしているクリーチャーが単独で攻撃するたび、それの上に+1/+1カウンター1個を置く。その後、諜報Xを行う。Xは、それの上にあるカウンターの個数に等しい。(あなたのライブラリーの一番上にあるカードX枚を見て、そのうち望む枚数をあなたの墓地に、残りをあなたのライブラリーの一番上に望む順番で置く。)


立身出世の犯罪者、トゥームストーン
(2)(黒)
伝説のクリーチャー - 人間(Human)・悪人(Villain)
2/2
これが戦場に出たとき、あなたの墓地にある悪人(Villain)カード1枚を対象とする。それをあなたの手札に戻す。あなたが悪人呪文を唱えるためのコストは(1)少なくなる。


モービウス・ザ・リヴィング・ヴァンパイア
(2)(青)(黒)
伝説のクリーチャー - 吸血鬼(Vampire)・科学者(Scientist)・悪人(Villain)
3/1
飛行、警戒、絆魂(青)(黒),あなたの墓地にあるこのカードを追放する:あなたのライブラリーの一番上にあるカード3枚を見る。そのうち1枚をあなたの手札に、残りをあなたのライブラリーの一番下に望む順番で置く。


スポットのポータル
(2)(黒)
インスタント
クリーチャー1体を対象とする。それをオーナーのライブラリーの一番下に置く。あなたが悪人(Villain)をコントロールしていないかぎり、2点のライフを失う。


無慈悲なるエンフォーサーズ
(1)(黒)
クリーチャー - 人間(Human)・傭兵(Mercenary)・悪人(Villain)
2/1
絆魂(3)(黒):このクリーチャーは各対戦相手にそれぞれ1点のダメージを与える。


蜂群人間、スウォーム
(2)(黒)
伝説のクリーチャー - 昆虫(Insect)・悪人(Villain)
2/2
瞬速飛行


スコーピオンの毒針
(1)(黒)
インスタント
クリーチャー1体を対象とする。ターン終了時まで、それは-3/-3の修整を受ける。


ヴェノムの飢え
(4)(黒)
ソーサリー
あなたが悪人(Villain)をコントロールしているなら、この呪文を唱えるためのコストは(2)少なくなる。クリーチャー1体を対象とする。それを破壊する。あなたは2点のライフを得る。
コモンにある《スコーピオンの毒針》と《ヴェノムの飢え》、アンコモンの《スポットのポータル》は黒を支える優秀な除去カードです。
相手のレア対策に除去はいくらでも必要。分かりやすく需要の高いカード群なので、これらが3手目あたりに流れてくれば、黒は空いていると考えて色替えも考慮したいです。
黒赤は不安定で形になりにくいので、青黒の形にするのが本命です。悪人が多いので部族デッキとしてまとめたり、除去とドローで重コントロールも狙えます。
青
メインカラーにするには不安が残るものの、サポートとして優秀な色です。


空飛ぶオクトボット
(1)(青)
アーティファクト・クリーチャー - ロボット(Robot)・悪人(Villain)
1/1
飛行あなたがコントロールしていてこれでない悪人(Villain)1体が戦場に出るたび、このクリーチャーの上に+1/+1カウンター1個を置く。この能力は、毎ターン1回しか誘発しない。
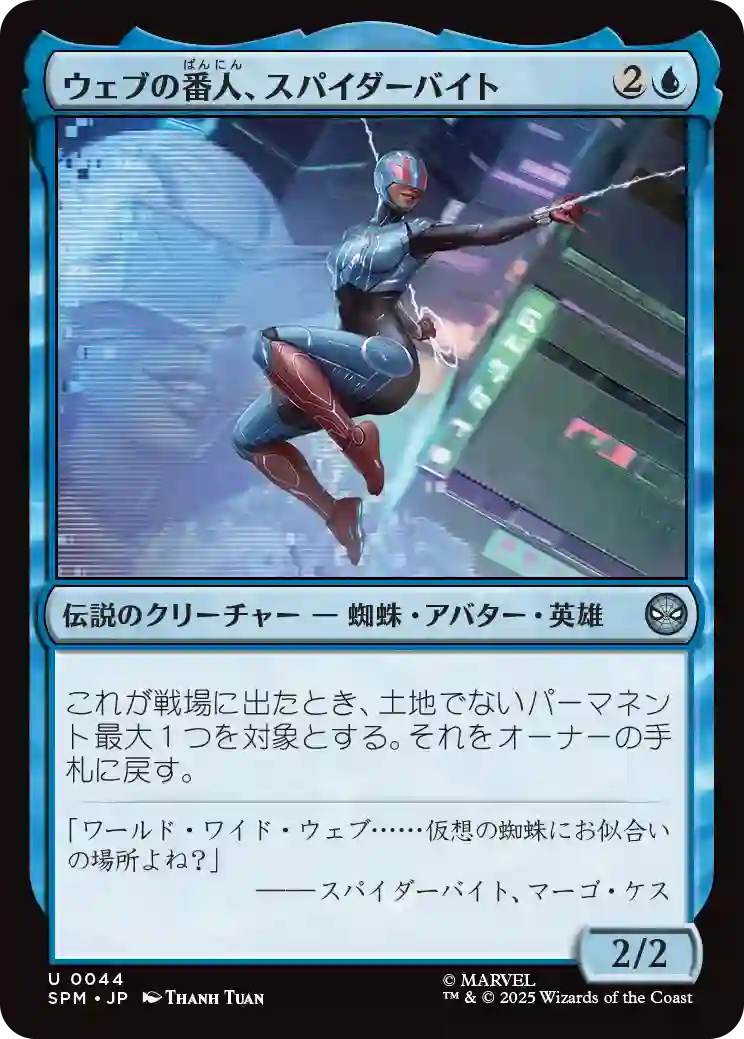
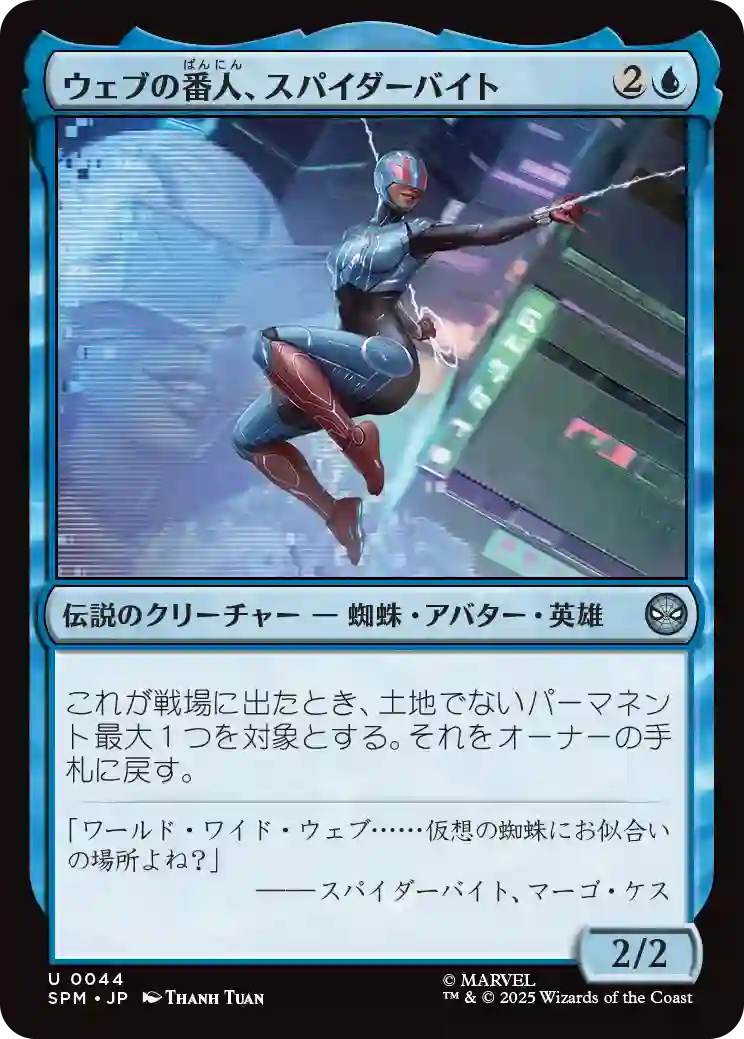
ウェブの番人、スパイダーバイト
(2)(青)
伝説のクリーチャー - 蜘蛛(Spider)・アバター(Avatar)・英雄(Hero)
2/2
これが戦場に出たとき、土地でないパーマネント最大1つを対象とする。それをオーナーの手札に戻す。


鉤爪の泥棒、プラウラー
(1)(青)(黒)
伝説のクリーチャー - 人間(Human)・ならず者(Rogue)・悪人(Villain)
2/3
威迫(このクリーチャーは2体以上のクリーチャーにしかブロックされない。)あなたがコントロールしていてこれでない悪人(Villain)1体が戦場に出るたび、これは謀議する。(カード1枚を引き、その後、カード1枚を捨てる。あなたが土地でないカードを捨てたなら、このクリーチャーの上に+1/+1カウンター1個を置く。)


ロボット工学の熟達
(4)(青)
エンチャント - オーラ(Aura)
瞬速エンチャント(クリーチャー)このオーラ(Aura)が戦場に出たとき、飛行を持つ無色の1/1のロボット(Robot)・アーティファクト・クリーチャー・トークン2体を生成する。


悪意ある科学者、ドク・オック
(4)(青)
伝説のクリーチャー - 人間(Human)・科学者(Scientist)・悪人(Villain)
4/5
あなたの墓地に8枚以上のカードがあるかぎり、これの基本のパワーとタフネスは8/8である。あなたがこれでない悪人(Villain)をコントロールしているかぎり、これは呪禁を持つ。(これは対戦相手がコントロールしている呪文や能力の対象にならない。)


ミステリオの幻
(1)(青)
クリーチャー - イリュージョン(Illusion)・悪人(Villain)
1/3
飛行、警戒このクリーチャーが攻撃するたび、カード1枚を切削する。(あなたのライブラリーの一番上にあるカード1枚をあなたの墓地に置く。)


アメイジング・アクロバティック
(1)(青)(青)
インスタント
以下から1つまたは両方を選ぶ。・呪文1つを対象とする。それを打ち消す。


不安定な実験
(1)(青)
インスタント
プレイヤー1人を対象とし、あなたがコントロールしているクリーチャー最大1体を対象とする。そのプレイヤーはカード1枚を引く。その後、そのクリーチャーは謀議する。(カード1枚を引き、その後、カード1枚を捨てる。あなたが土地でないカードを捨てたなら、そのクリーチャーの上に+1/+1カウンター1個を置く。)
主力になるのは飛行を持ったクリーチャー群で、コモンの《ミステリオの幻》とアンコモンの《空飛ぶオクトボット》は、地味にライフを削る能力があります。
白青だと+1/+1カウンターを載せてみたり、青黒だと墓地から使える起動能力や悪人シナジーを利用できるので、見た目よりも影響力があります。
欠点は除去の弱さであり、今回は2マナの不確定カウンターすらありません。レアが強い環境だと、カウンターも有用なケースが多いのですが、ダブルシンボル3マナの《アメイジング・アクロバティック》だと、後手で構えるのがしんどいケースがあります(もちろん強いんですが)。
白や黒のサポート色として、飛行の水増し、+1/+1カウンターの利用、悪人の部族シナジーの確保などに役立つものの、メインカラーにするにはアンプレ1なカードが多いので注意が必要です。
赤
今回の露骨なルーザーカラーで、迂闊に参入すると火傷する色です。


怒り狂うゴブリノイド
(4)(赤)
クリーチャー - ゴブリン(Goblin)・狂戦士(Berserker)・悪人(Villain)
5/4
速攻大混乱(2)(赤)(このターンにあなたがこのカードを捨てていたなら、墓地にあるこれを(2)(赤)で唱えてもよい。タイミングのルールは適用される。)


揺るがぬ者、ショッカー
(4)(赤)(赤)
伝説のクリーチャー - 人間(Human)・ならず者(Rogue)・悪人(Villain)
5/5
あなたのターンの間、これは先制攻撃を持つ。振動波ガントレット ― これが戦場に出たとき、クリーチャー1体を対象とする。これはそれに2点のダメージ、そのクリーチャーのコントローラーに2点のダメージを与える。


気の利いた軽口
(2)(赤)
インスタント
クリーチャー1体を対象とする。それは自身に、それのパワーに等しい点数のダメージを与える。そのクリーチャーが攻撃しているなら、気の利いた軽口はそのクリーチャーのコントローラーに2点のダメージを与える。


エレクトロの電撃
(2)(赤)
ソーサリー
クリーチャー1体を対象とする。エレクトロの電撃はそれに4点のダメージを与える。大混乱(1)(赤)(このターンにあなたがこのカードを捨てていたなら、墓地にあるこれを(1)(赤)で唱えてもよい。タイミングのルールは適用される。)
まずコモンのカードが軒並みアンプレよりであり、入れるとしても3マナ4点の《エレクトロの電撃》くらいという悲惨な状況になっています。再録されている《ショック》も環境的に刺さりにくいです。
アンコモンについては3マナで5/4速攻の《怒り狂うゴブリノイド》や、2点火力を内蔵した《揺るがぬ者、ショッカー》など有力なカードはあるものの、それだけで参入するにも怖さがあります。
特に赤黒の形はテーマの大混乱が不安定なので、戦績を安定させるのが難しいです。正直、レアありきだと思います。
相方に緑を選ぶ場合、更に色を足すなどして戦力不足を補いたいですし、デッキ中の赤が濃い程に勝率が下がる傾向にあります。
今回のボムレア
蜘蛛を貪る者、モーラン

蜘蛛を貪る者、モーラン
(X)(黒)(黒)
伝説のクリーチャー - 吸血鬼(Vampire)・悪人(Villain)
2/1
絆魂これは+1/+1カウンターX個が置かれた状態で戦場に出る。
強力なレアが多い環境なんですが、その中でも飛びぬけた強さを持っている1枚です。
本体X点のドレインがゲームを決めることが多く、場に残るとダメージレースを崩壊させる大型の絆魂生物になります。バウンス、墓地回収、ウェブスリングで再利用できれば更なる活躍も見込めます。
黒のダブルシンボルではありますが、緑絡みだとピック次第で普通にタッチできるので、採用できるデッキは意外と広いです。
狡猾な怪盗、ブラックキャット

狡猾な怪盗、ブラックキャット
(3)(黒)(黒)
伝説のクリーチャー - 人間(Human)・ならず者(Rogue)・悪人(Villain)
2/3
狡猾な怪盗、ブラックキャットが戦場に出たとき、対戦相手1人を対象とする。そのプレイヤーのライブラリーの一番上にあるカード9枚を見て、そのうちの2枚を裏向きで追放する。その後、残りをそのライブラリーの一番下に無作為の順番で置く。それらのカードが追放され続けているかぎり、あなたはそれらのカードをプレイしてもよい。これにより呪文を唱えるために任意のタイプのマナを支払ってもよい。
やっぱり強力な黒のレアで、相手のデッキの上から9枚を見て、そのうち2枚を奪い取れるというトンデモなカードです。
抱き合わせだけあってコストパフォーマンスに優れており、《食料補充(DFT)》の強化版に2/3クリーチャーが付いてきます。
リミテッドではデッキの中の強いカードは限られているので、それを相手のデッキから奪い取って、将来的な脅威を軽減できるという点も優秀です。
- アンプレ: アンプレイアブルの略。実戦レベルにないカードのこと。 ↩︎










関連の人気投稿